今日は何の日をAI熊猫まる(パンダ)で表現⁉:1月9日は、「クイズの日 / とんちの日」です。 一休さんの語呂合わせで制定された記念日です。一休さんは室町時代に実在した臨済宗の僧で、とんち話の題材として有名です。
「クイズの日 / とんちの日」とは
「クイズの日 / とんちの日」とは、1月9日に制定された記念日です。この日は、「いっ(1)きゅう(9)」と読む語呂合わせから、室町時代に活躍した臨済宗の僧で、とんち話の主人公として有名な一休さんにちなんでいます。
「とんち」とは、その場に応じてすぐに出てくる知恵で難題を解決したり、相手をやり込めたりすることを意味します。一休さんは、権力や戒律にとらわれない自由奔放な生き方をし、とんちで人々を笑わせたり、時には社会を風刺したりしました。彼の逸話は、日本の昔話の代表的なものとして、今もなお多くの人々に親しまれています。
「クイズ」とは、もともと英語で「質問すること」や「知識をテストすること」を意味する言葉です。日本では「知識を問う問題」として親しまれ、教育や娯楽の場において活用されています。クイズは、知識や思考力を試すだけでなく、コミュニケーションのツールとしても重宝されており、家族や友人との楽しい時間を演出する手段としても用いられています。
「とんちの日 / クイズの日」は、とんちの精神がクイズにも通じるという考えから、同じ日に呼ばれるようになりました。即座に答えを見つける機敏さや、知識を結びつける創造力は、とんちとクイズの両方に共通する要素です。この記念日は、とんちのある人を讃える日として、また、日常生活におけるとんちやクイズの大切さを再認識する機会として捉えることができます。
一休さんの生涯について
一休さんは、室町時代に活躍した臨済宗の僧で、詩人でもありました。彼は天皇の落胤という伝説があり、幼い頃から才能に恵まれていました。しかし、権力や戒律にとらわれない自由奔放な生き方をし、とんちで人々を笑わせたり、時には社会を風刺したりしました。彼の生涯は、以下のようにまとめることができます。
- 6歳で安国寺の僧になり、周建と名付けられる。
- 17歳で謙翁宗為の弟子となり、戒名を宗純と改める。
- 22歳で大徳寺の高僧、華叟宗曇の弟子となる。公案に答えて一休の道号を授かる。
- 27歳でカラスの鳴き声を聞いて悟りを開く。印可状を辞退する。
- 34歳で華叟宗曇が亡くなり、旅に出る。数々の逸話や作品を残す。
- 80歳で後土御門天皇の勅命で大徳寺の住持になる。塔頭の真珠庵を創建する。
- 87歳で酬恩庵で亡くなる。墓は酬恩庵にある。
一休さんが風刺した社会とは
一休さんは、室町時代の社会を風刺した詩や狂歌を多く残しています。彼が風刺した社会とは、以下のような特徴を持つ社会です。
- 仏教の権威や戒律が形骸化し、僧侶が世俗的な生活を送っている社会。例えば、一休さんは「釈迦といふ いたづらものが世にいでて おほくの人をまよはするかな」と詠んで、仏教の教えが人々を惑わせていると批判しました。
- 戦乱や飢饉に苦しむ民衆と、贅沢や権力争いにふける貴族や武士の間に格差が広がっている社会。例えば、一休さんは「世の中は起きて箱して(糞して)寝て食って後は死ぬるを待つばかりなり」と詠んで、人々の生活の虚しさや無意味さを風刺しました。
- 美や芸術に対する感性や情趣が失われ、外面や形式にこだわる人が多い社会。例えば、一休さんは「えりまきの 温かそうな 黒坊主 こいつの法が 天下一なり」と詠んで、本願寺の僧侶の姿をからかいました。
一休さんの詩
一休さんは詩人としても有名で、漢詩や狂歌などを多く残しています。彼の詩は、禅の教えや風刺、自然や人生の情趣などを表現しています。一休さんの詩の中から、いくつかを紹介しますね。📚
- 『長門春草』:一休さんが13歳の時に作った漢詩です。京都の長門神社の春の風景を詠んでいます。この詩は、中国の古典をも踏まえており、当時、京で非常な評判になりました。
長門春草
長門神社春草青
花開梅柳風光明
遊人笑語聲相接
鳥啼花落日西傾- 『春衣宿花』:一休さんが15歳の時に作った漢詩です。春の夜に花の下で眠る自分の姿を詠んでいます。この詩は、自然と人間の一体感や、春の情趣を表現しています。
春衣宿花
春衣宿花花下眠
夢中無事任春風
夜深月落花成雪
不覺寒潮濕春衣- 『一休骸骨』:一休さんが晩年に作った漢詩です。自分の死を予感して、自らの骸骨を描いた絵に詩を添えたものです。この詩は、一休さんの自由奔放な生き方や、死に対する態度を表現しています。
一休骸骨
骸骨一具是吾身
不知何日化為塵
世間萬物皆如此
何必憂愁苦惱人一休さんの狂歌
一休さんは狂歌という、三十一文字で自由に詠む歌を多く残しています。彼の狂歌は、禅の教えや風刺、自然や人生の情趣などを表現しています。一休さんの狂歌の中から、いくつかを紹介しますね。📚
- 正月は冥途の旅の一里塚 めでたくもありめでたくもなし:一休さんが骸骨の付いた杖で街を練り歩きながら詠んだという狂歌です。正月のめでたさと、人生のはかなさを対比させています。
- 釈迦といふいたずらものが世にいでて おほくの人をまよはするかな:一休さんが仏教の教えが人々を惑わせていると批判した狂歌です。釈迦を「いたずらもの」と呼ぶのは、一休さんの反骨精神を表しています。
- 雪の降る日引導せられし時 鍬の先抜けけるに詠める:一休さんが死に際して詠んだという狂歌です。鍬の先が抜けるというのは、自分の墓を掘っているときに起こったことを意味しています。一休さんは死を恐れず、冷静に受け入れていました。
一休さんととんちの話をしているパンダのイラスト写真
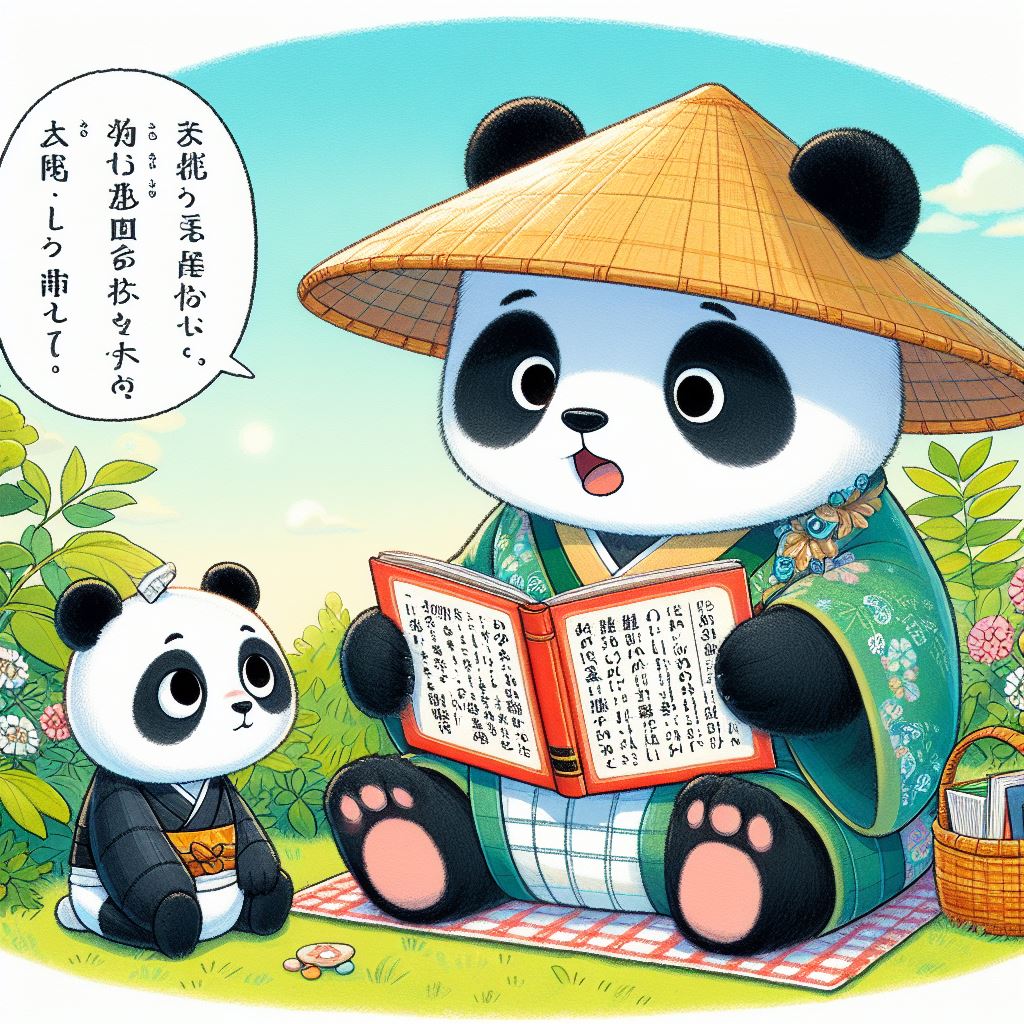

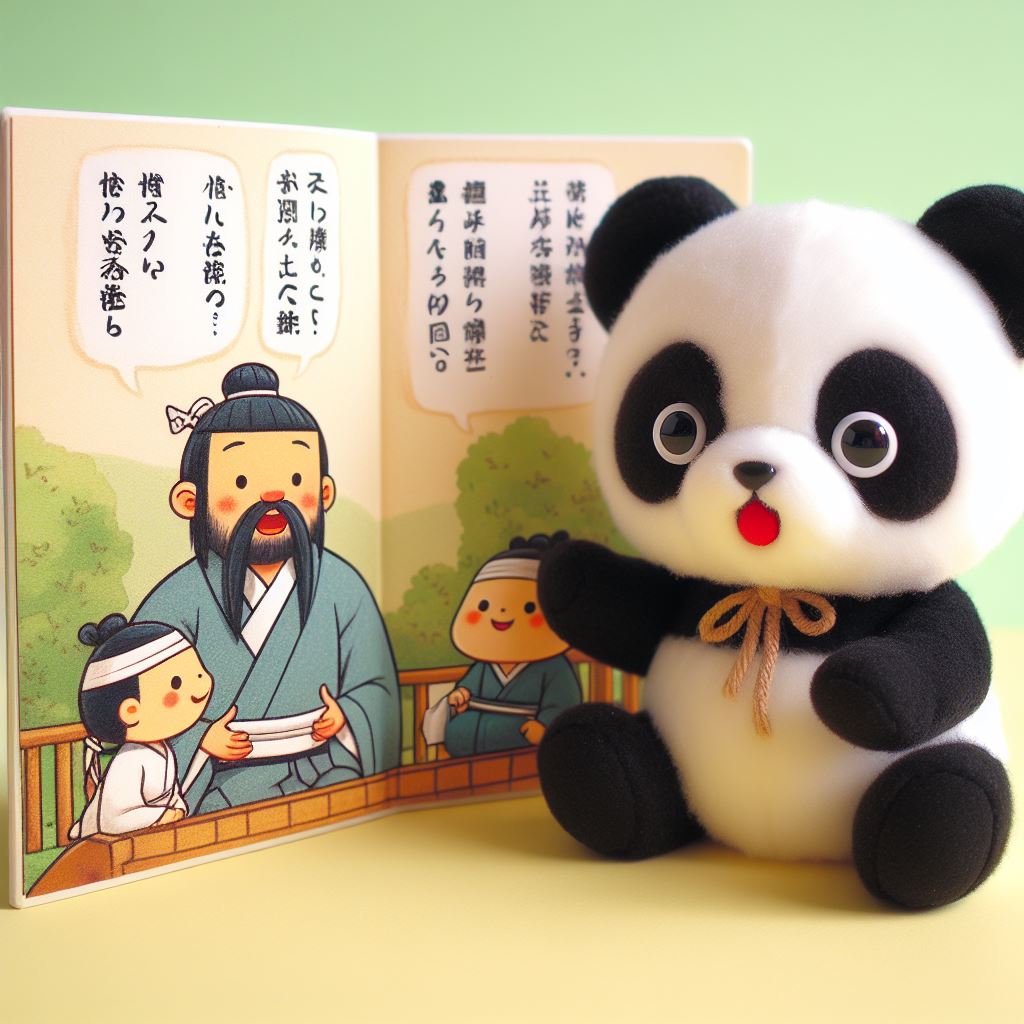










コメント