72候は日本の伝統で、1年を72の時期に分けて、季節の変化を細かく捉えます。卯月(4月)は、自然が活発になる春本番を表します。この時期、ツバメが北から帰ってきて巣作りを始め、新緑が目を引きます。雨が多く、虹を見ることもあります。卯月をさらに5つに細分化し、桜の開花や春雷の始まりなど、自然の具体的な変化を表しています。72候は四季の美しさを深く感じさせ、私たちに自然の循環を教えてくれます。
目次
卯月について
「卯月」について説明します。
- 卯月とは何月?
- 「卯月」は、4月の別名です。
- 旧暦では、卯月は4月下旬から6月上旬にあたりますが、現代の新暦(グレゴリオ暦)では4月と同じ意味で使われています。
- 卯月の意味と由来
- 由来は諸説ありますが、いくつかの説があります:
- 「植え月」説: 旧暦の卯月は稲の種を植える時期であることから、「植え月」とされています。
- 「はじまりの月」説: 古代日本では卯月を一年の初めとみなす考え方があり、「はじまりの月」とされています。
- 「ウツギの花」説: ウツギの花がこの時期に咲くことから、「ウツギの月」とも言われています。
- 「十二支の卯」説: 卯月は十二支の4番目である「卯」から取られたとも言われています。
- 由来は諸説ありますが、いくつかの説があります:
- 卯月の別名
- 卯月にはさまざまな別名があります:
- 夏初月(なつはづき): 夏の最初の月を意味します。
- 初夏(しょか、はつなつ): 夏の初めを表します。
- 乏月(ぼうげつ): 穀物が乏しくなる月です。
- その他にもさまざまな別名があります。
- 卯月にはさまざまな別名があります:
- まとめ
- 卯月は、新しい始まりや季節の変わり目を感じる特別な月です。
72候の「玄鳥(ツバメ、ツバクラメ)」について

玄鳥(つばめ)と七十二候について説明しますね。
- 玄鳥(つばめ)とは?
- 玄鳥は、ツバメの別名です。
- ツバメは、春から夏にかけて軽やかに空を舞う姿を見せてくれる鳥です。
- 玄鳥去る(つばめさる)とは?
- 玄鳥去るは、七十二候の第四十五候の季節です。
- この時期、燕(ツバメ)が南へ帰って行く様子を表現しています。
- ツバメは冬のために台湾やフィリピン、マレー半島などの東南アジアへ移動します。
- なぜツバメは南へ帰るの?
- ツバメは寒さに弱いため、冬の寒い日本を避けて暖かい地域へ移動します。
- この長い旅をするツバメの生命力に驚かされます。
- まとめ
- 玄鳥去るは、秋の訪れとともにツバメが南へ渡る季節です。
- ツバメの姿を見ると、季節の変化を感じることができますよ!
72候の「たらのめ」ついて

もちろんです!たらのめは、日本の伝統的な暦で使われる言葉で、4月を指します。以下に、七十二候と結びつけて説明しますね。
- 玄鳥至(つばめきたる)(4月5日頃)
- 燕が南の国から渡ってくる頃。
- 「玄鳥」は燕の異名です。
- 蚯蚓出(みみずいずる)(4月10日頃)
- みみずが地上に出てくる頃。
- 畑土をほぐしてくれるみみずは、動き始めるのが少し遅めです。
- 菖蒲華(あやめはなさく)(4月15日頃)
- あやめの花が咲き始める頃。
- 端午の節供に用いる菖蒲ではなく、花菖蒲のことです。
たらのめは、春の訪れを感じる大切な野菜で、食べ方もさまざまです。
72候の「虹」ついて

虹について説明します。
- 虹ができる理由
- 虹は、太陽の光と雨粒との関係にあります。
- 太陽の光は「白色光」で、さまざまな色の光が混ざってできています。
- 雨粒の中で光は反射・屈折し、色ごとに光の進む方向が変わり、七色の虹ができます。
- 虹が見える場所や時間の特徴
- 自然が豊かな場所や海辺でクリアな虹を見ることができます。
- 雨上がりの午後や早朝に虹を見ることが多いです。
- 大きな虹と小さな虹
- 雨粒の中で光が1回反射すると大きな虹が、2回反射すると小さな虹ができます。
- 虹を鮮やかに見るコツ
- 太陽の反対側を見ると虹が見える確率が高くなります。
- 空が暗く、雨粒が大きいときに鮮やかに見えます。
虹は自然の不思議で、雨上がりの空を楽しんでくださいね!
「清明(せいめい)」について

もちろんです!清明(せいめい)は、二十四節気のひとつで、春の季語でもあります。以下に、清明の初侯、次候、末候について詳しく説明しますね。
- 初侯:玄鳥至(つばめきたる)(4月4日頃)
- 燕が南の国から渡ってくる頃。
- 「玄鳥」は燕の異名です。
- 次侯:鴻雁北(こうがんかえる)(4月9日頃)
- 雁(がん、かり)が北へ帰っていく頃。
- 雁は冬場は日本、夏場はシベリアで過ごす渡り鳥です。
- 末侯:虹始見(にじはじめてあらわる)(4月14日頃)
- 雨上がりに虹が見え始める頃。
- 淡く消えやすい春の虹が、次第にくっきり見えるようになってきます。
「穀雨(こくう)」について

穀雨は、日本の伝統的な暦で使われる言葉で、4月を指します。以下に、穀雨の初侯、次候、末侯について詳しく説明します。
- 初侯:葭始生(あしはじめてしょうず)(4月19日頃)
- 水辺の葭が芽吹き始める頃。
- 葭はイネ科の多年草で、夏に背を伸ばし、秋に黄金色の穂をなびかせます。
- 夏の暑さを遮る「葭簀(よしず)」の原料です。
- 次候:霜止出苗(しもやみてなえいずる)(4月25日頃)
- 霜が降らなくなり、苗代で稲の苗が生長する頃。
- 霜は作物の大敵とされています。
- 末侯:牡丹華(ぼたんはなさく)(4月30日頃)
- 牡丹が豪華な花を咲かせる頃。
- 豪華で艶やかな牡丹は「百花の王」と呼ばれています。





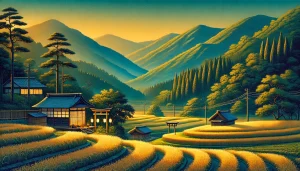
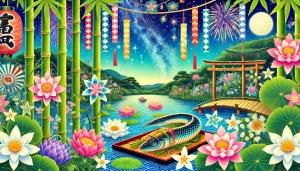


コメント